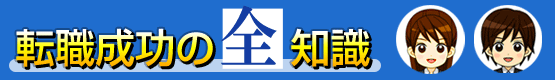住民税は前年の所得にかかる
住民税は前年の所得を元に課税されます。
つまり退職して失業状態になっても、現在では無く前年の所得にかかる税金ですから、たとえ失業中で収入が無くても住民税は必ず支払わなければなりません。
住民税は決して安くは無く失業の身には辛い金額ですが、こればかりは避けられません。
退職した場合、住民税の引継ぎはどうなる?
住民税は、会社に在職していれば前年の所得から計算して6月から翌年5月までの1年間、毎月の給料から徴収されます。
前年の所得に対する住民税の支払い時期の考え方は下の図のようになります。
所得と住民税の支払いの時期の考え方

しかし会社を退職すると、給料から差し引くことが出来なくなるため、納付通知書にしたがって自分で収めなければならなくなります。
ただ、住民税は退職した時期(月)によって納め方が変わってきます。
それぞれのケースでの住民税の納め方を説明します。
1月~4月の間に退職した場合
1月~4月の間に退職した場合、住民税の残高(住民税は6月~翌5月までの1年間で給料から徴収されるので「住民税の残高」とは退職した月から5月徴収分までの合算)をまとめて退職した月の給料、または退職金から差し引かれます。
つまり1月に退職すると、1月から5月までの5ヶ月分の住民税がまとめて差し引かれることになります。
1月~4月の間(図では2月)に退職した場合
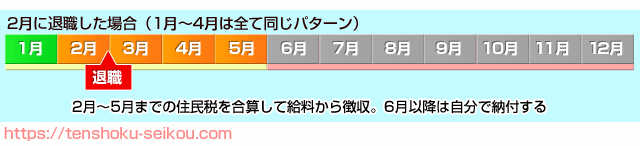
5月に退職した場合
5月に退職した場合は通常通り1ヶ月分(5月分)の住民税を差し引かれます。
5月に退職した場合

6月以降に退職した場合の住民税は会社を通してではなく、あなた自身が支払うことになります。
この場合、退職後、あなたの自宅に「納税通知書」が送られてきますから、その通知書の方法に従って支払います。
ただし6月以降の退職であっても、あなたが「住民税の残高をまとめて退職月の給与(もしくは退職金)から支払いたい」と会社に希望を申し出た場合は一括で支払うことも可能です。
6月以降(図では6月)に退職した場合
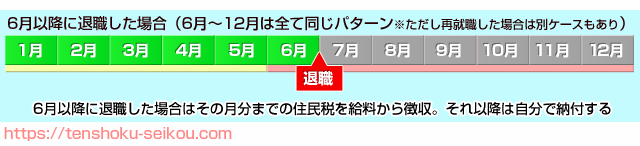
なお、会社の給料から住民税を徴収することを「特別徴収」と言い、納税通知書にしたがって自身で納めることを「普通徴収」と言います。
退職後すぐに再就職が決まった場合
前の会社を退職して、期間を空けず直ぐに再就職先が決まった場合、再就職した会社の給料から住民税の「特別徴収」を引継ぎが出来る場合がありますので確認してみてください。
ただ、私の経験上、こちらから確認しなくても、新しい職場の経理の人から「引継ぎますか(特別徴収)?それとも前年分は自分で納めますか(普通徴収)?」と聞かれると思います。
どちらを選択しても構いませんが、その時点で蓄えが無いようなら、会社で特別徴収での支払いを引き継いでもらった方が無難だと思います。