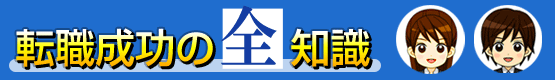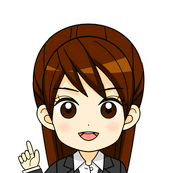
退職金にも税金はかかりますが税率は軽いです
退職金にも所得税、住民税の両方が課税されます。
ただし退職金に関しては、給与などとは別の所得として課税される「分離課税方式」で徴収されますので、給与にかかる税率とはかなり違ってきます(負担は軽くなります)。
退職金にかかる所得税は、あなたの勤務年数に応じて計算された「退職所得控除額(勤務年数が長いほど控除される)」を差し引いた額の2分の1が課税対象になりますが、そもそもこの「退職所得控除額」が高く設定されており、さらに課税対象は、その控除後の金額の2分の1ですから、結果的に退職金にかかる税金は軽くなるようになっています。
退職にかかる所得税の計算方法
下が退職金の所得税の算出方法です。
※退職金所得控除額は(退職金を払った)会社での勤続年数により算出されます。
退職にかかる住民税の計算方法
退職金の住民税は課税対象金額から「市町村民税(6%)」と「都道府県民税(4%)」が徴収されます。
まず、退職金の課税対象金額は以下の計算式で算出します。
この課税対象金額に「市町村民税(6%)」と「都道府県民税(4%)」とのがそれぞれ徴収されることになります。
都道府県民税=課税対象金額×0,4
自分で確定申告しなくてもよいようにする
退職金にかかる税金は、会社から退職金が支払われる段階で徴収されます。
ただしこの時、あなたが会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているか、いないかによって、後々あなた自身で確定申告をする必要が出てきます。
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば確定申告をする必要はありません。
というのも「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出している人の場合、会社が退職金を支払う段階で勤続日数に基づいて退職所得控除額を差し引いた額をもとに税額が計算された後、源泉徴収をされるからです。
しかし「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないと、退職金全部に20%をかけた額に所得税が源泉徴収されるため、本来の退職金の税率よりも多く徴収されてしまいます。
そのため、この多く徴収された分の税金を取り戻すために確定申告をしなければならなくなるのです。
どちらの方法が良いかは人それぞれですし、会社の都合もあるかと思いますが、自分で確定申告をするのが面倒だという人は「退職所得の受給に関する申告書」を提出しておきましょう。