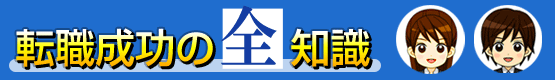会社の倒産はめずらしいことではない
「中小企業が会社設立から10年で倒産する確率は90%以上」
という衝撃的なデータがあります。
これには2006年5月に施行された「新会社法」によって、1円で株式会社が設立出来るようになったことや、インターネットで利益を上げる方法が確率され、IT系の会社が次々と設立されたことも要因として挙げられます。
こういった事実からも、自分が勤務している会社がある日突然倒産するということは、今や決してめずらしいことでは無く、誰にでも起こり得ることだということはお分かりいただけると思います。
事実、私が正社員として勤務していた2つのIT関連の会社のうちの一つは倒産してしまい、今はもうありません。
さらに、私がはじめてアルバイトとして「WEBサイト作成」の実務を経験させていただいた会社にいたっては、私が辞めた3、4年後には億を超える負債を抱えて破産してしまいました。
(幸い?)どちらも私が在職中の倒産ではありませんでしたが、約十年という短い間に私が在籍した3つの会社のうち2つが倒産したわけですから、その確率の高さはお分かりいただけると思います。
会社が倒産してしまったら未払い金はどうなるのか?
勤務していた会社が倒産してしまったときに最も気になるのは、未払い分の給料は払ってもらえるのか?退職金は払ってもらえるのか?ということだと思います。
会社が倒産してしまった場合、会社に財産が残っていれば、優先的に未払い分の給与や退職金の一部の支払いを受けることが出来ます。
ただし会社には税金や社会保険料の滞納分の支払い義務もありますから、会社に残っている財産すべてが給与等の未払いに充てられるわけではありません。
では会社に財産が残っていない場合はどうなるのでしょうか?
その場合、政府が「立替払い」で、あなたの未払い分の給与を保障することになります。
政府があなたの未払い金を保障する立替払い制度
会社が倒産して給与などの未払い金が発生した場合は、政府が立替払いをしてくれることがあります。
立替払いを受けるには条件があり、また全額を保障してくれるわけではありません。
ただそれでも全く貰えないことを考えれば十分価値のある制度です。
立替払いを受ける条件は下記になります。
(1)労災保険に1年以上加入している事業所(個人・法人問いません)に労働者として雇用されてきたこと。
(2)倒産によって退職し「未払い賃金」が残っていること
(3)倒産した日の6ヶ月前の日から、2年以内に退職した労働者であること
では順に解説します。
(1)労災保険に1年以上加入している事業所(個人・法人問いません)に労働者として雇用されてきたこと
希に労災保険に加入せず事業を続けている会社がありますが、こういった会社が倒産した場合は
未払い金が発生しても立替払いを受けることは出来ません。
また、加入している会社であっても1年以上加入していなければ、同じく立替払いを受けることは出来ません。
(2)倒産によって退職し「未払い賃金」が残っていること
これは当然ですね。未払い金が残っていなければ立替払いを受けることは出来ません。
(3)倒産した日の6ヶ月前の日から、2年以内に退職した労働者であること
これは「裁判所に対する破産などの申立日、または労働基準監督署長に対する倒産の事実についての認定申請日の
6ヶ月前の日から2年の間に退職した人であること」という意味です。
裁判所や労働基準監督署長に申請する前であっても、会社が事実上の倒産状態に陥り、賃金の支払いが滞ることはあり得ます。
そんな場合も、この(3)によって保障してもらえるということです。
立替払いを受ける条件:退職時期

立替払い制度の上限額
立替払いには上限額があります。
下の図を参考にしてください。
未払い金の上限額と立て替え金の上限額

立替払いの請求方法
立替払いの請求は、破産宣告の日の翌日から2年以内に「労働者健康福祉機構」に請求しなければなりません。
この場合、まずは会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談すれば、ケースによってその後どう行動すれば良いか指導してもらえます。
また、破産管財人がいる場合はあなたに代わって手続きをしてもらえることもありますから確認してみてください。
会社が倒産しそうだと感じた時点で、転職サイトには必ず登録しておきましょう。
登録はスマホから簡単にできます。
もちろん利用は完全に無料です。
転職サイトは登録の際にプロフィールを登録しますから、登録だけでも済ませておけば「スカウト」が来るかもしれません。
また、転職サイトは求人募集の数がハローワークや転職エージェントと比べても圧倒的に多いですから、どんな仕事があるのか確認するだけでも視野が一気に広がると思います。
転職サイトはリクルートが運営する「リクナビNEXT」が求人数が圧倒的に多く、採用されやすい求人も多いのでオススメです。まずは登録して、あなたの通勤圏内でどういった求人があるか確認してみてください。