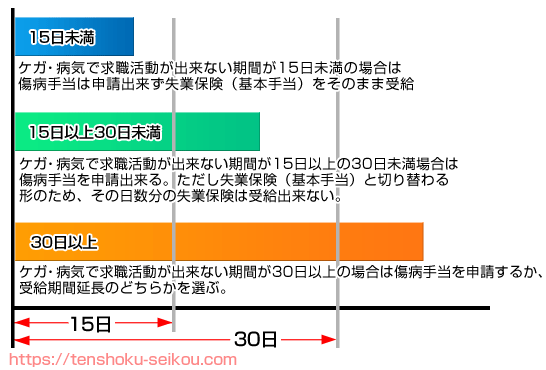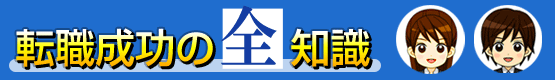(1)失業保険の受給期間の延長
(2)傷病手当の申請
のどちらかの選択肢があります。
選択肢.1 失業保険の受給期間の延長する
離職後すぐに求職活動が出来ない場合の選択肢の一つで「受給期間の延長」があります。
「受給期間を延長」とはどういう意味か解説します。
基本的に失業保険の受給期間(期限)は離職翌日から1年間ということはご存知ですよね?
失業保険の支払対象日数が90日だった場合、仮に失業保険の申請自体が遅れ、結果、離職翌日から305日後からようやく失業保険が支給されたとすると、1年は365日ですから残りは60日しか無く、(支払対象日数90日の内)60日分の失業保険は支給されますが、残りの30日分は失効してしまうことになります。
こういうことにならないために離職後すぐに求職活動が出来ない場合は「1年」という受給期間の延長を申請するのです。
受給期間の延長が認められるケースとしては
・出産
・育児(3歳未満の乳児に限る)
・疾病・負傷
があります。
受給期間延長の申請方法
受給期間の延長は管轄のハローワークに「受給期間延長申請書」を提出します。
申請用紙はハローワークでもらえます。
その際「延長理由が確認できる書類」と「離職票-1」「離職票-2」が必要になりますので、退職後に会社から送られてくる離職票1、2は無くさないようにしてください。
なお、この受給期間の延長申請には期限があります。
延長理由が認められる理由が30日以上継続する場合、その30日を経過した日から1ヶ月以内に申請手続きを行わなければなりません。
ただしこの受給期間の延長申請は、そもそもの理由がケガや出産だった場合、本人がハローワークに行けないこともあり得ます。
そのため代理人による提出、もしくは郵送も認められています。
選択肢.2 傷病手当を申請する
離職後すぐに求職活動が出来ない場合のもう一つの選択肢として「傷病手当の申請」があります。
ただしこちらは読んで字のごとく「病気・ケガ」の場合に限られます。
また、病気やケガで求職できない期間が15日未満の場合は該当しません。
15日未満の場合は特に申請する必要もなく、通常通り失業保険の支給を受けることになります。
15日以上30日未満病気やケガで求職活動が出来ないとき
病気やケガで15以上30日未満の間求職活動が出来ない場合は、失業保険の代わりに傷病手当が支給されます。
傷病手当の支給額は失業保険の支給額と変わりません。
つまり「呼び方が代わっただけ」という捉え方で構いません。
ですから傷病手当が支給されれば、その日数分の失業保険も支給されたことと同じ扱いになり、傷病手当と失業保険の両方を受け取ることは出来ません。
申請は病気やケガが治った最初の認定日までに「傷病手当支給申請書」と「受給資格証」をハローワークに提出します。
30日以上病気やケガで求職活動が出来ないとき
病気やケガで30日以上求職活動が出来ない場合は、先ほど説明した「受給期間の延長」か「傷病手当」のどちらかを選ぶことになります。
どちらを選ぶべきかはケース・バイ・ケースで私が明言することは出来ませんが、治療にそれなりの時間がかかりそうな場合や、いつ求職活動が出来るか分からないような場合は「受給期間の延長」を選んだほうが賢明かもしれません。
また(求職活動が出来ない理由となる病気やケガに対して)他の社会保険から給付が受けられている場合は、傷病手当は支給されませんから、こういった場合も「受給期間の延長」を選んで、後に「求職の申込」をしたほうが賢明なように思います。
なお、30日以上病気やケガで傷病手当を申請する場合は、先ほど説明した「15日以上30日未満~」の申請方法と同様になります。
求職活動出来ない期間と傷病手当、または受給期間延長の関係を下の図でまとめました。参考にしてください。
求職活動が出来ない期間と傷病手当の関係